日本では1月1日が年の始まりですが、学校や会社の新たな区切りは4月から始まるのが一般的です。
このタイミングを「新年度」や「年度初め」と呼び、入学式や入社式といった行事もこの時期に集中しています。
日本において、4月にスタートを切ることが定番となっているのは何故なのでしょうか?
本記事では、主に日本において、多くの行事が春(4月)に始まることが多いのかなどについて説明していきます。(※なお、この記事では「年度初め」と表記していますが、「年度始め」と書くことも可能で、どちらを使っても問題ありません。)
「年度」とは何なのか?
「年度」(ねんど)とは、特定の目的に応じて区切られた1年間の期間を指します。
この言葉は、特に国や自治体の予算管理に使われる「会計年度」や、学校で学年を区切る「学校年度」などでよく登場します。
これらの年度は、一般的に4月から翌年3月までを1サイクルとしています。
多くの場合、「年度」と聞けば4月スタートの期間を思い浮かべますが、実は用途によって異なる年度設定も存在しています。
例えば、「麦年度」は7月から翌年6月、「いも年度」は9月から翌年8月、「大豆年度」は10月から翌年9月、そして「米穀年度」は11月から翌年10月までとされています。
日本で新しい年度が4月に始まるのは何故なのか?
日本では、学校も企業も4月から新しい一年が始まるのが一般的です。
学校年度も会計年度も4月から翌年3月までを一つの区切りとしています。
そして、入学式や入社式などの大切なイベントも、ほとんどがこの季節に行われます。
会計年度が4月スタートになった背景には、1886年の制度改正が関係しています。
当時、秋に収穫を迎える米作が税の中心だったため、秋に収穫し、それを反映した税金を春に納める流れが合理的と考えられたのです。
さらに、当時影響力の大きかったイギリスが4月を会計年度の始まりとしていたことも、日本が4月スタートを採用した理由の一つでした。
一方、学校の新学年についても、明治時代末期に会計年度と歩調を合わせるために4月入学が推進されました。
また、試験を行う6月がちょうど梅雨の時期に重なることから、4月入学にすることで学生たちの健康管理もしやすくなる、という配慮もありました。
こうした歴史的な背景が積み重なり、今では4月が日本における新たな門出の象徴となっているのです。
新年度に関する歴史背景について
日本の新年度が4月から始まる背景には、明治期に制定された会計年度が大きく関係しています。
会計年度が4月スタートとなったため、学校年度もそれに合わせて整備され、全国的に統一されていきました。
この制度は昭和の時代には定着し、戦後の経済成長とともに、新卒者が4月に一斉に就職するスタイルも定着、企業も4月を新年度の区切りとするようになりました。
ちなみに、世界的には「新学期が9月に始まる国」が多いというのが一般的です。
日本国内でも、9月入学への移行が議論されたことがありますが、春の桜とともに行われる卒業式や入学式が文化として根付いているため、4月スタートは日本ならではの風習として大切にされています。
真夏の終わりに新たな学年が始まるというスタイルは、日本人にはまだなじみが薄いと言えるでしょう。
学校年度の歴史遍歴
日本の学校における「年度」は、時代とともに形を変えてきました。
江戸時代の寺子屋や明治初期の教育機関では、入学や進級のタイミングに特に決まりがなく、生徒は好きな時期に入学し、それぞれの進度に応じて進級していました。
しかし、大学制度が整備されると、海外の教育システムにならって「一斉入学・一斉進級」が取り入れられました。
最初の頃は9月から8月までを学年とする運営が行われていましたが、明治19年(1886年)の会計年度の制定に合わせ、学校年度も4月開始に変更されました。
この変更は、政府や自治体から支給される補助金の管理と歩調を合わせるために推し進められ、全国的に浸透していきました。
また、9月始まりの制度では、梅雨の時期に学年末試験を実施することになり、生徒の健康に配慮する面からも、4月入学が望ましいと考えられるようになりました。
さらに、明治時代に施行された徴兵制度も、学校年度に大きな影響を与えました。
徴兵検査の届け出日が9月1日から4月1日に繰り上げられたことで、教育機関もスケジュールを見直し、4月スタートの新学期が主流になっていったのです。
会計年度の歴史遍歴
日本の会計年度が現在の形になったのは、明治19年(1886年)のことです。
当時の日本経済は稲作中心で、国家の財政も農民が納める米の税金に大きく支えられていました。
米は秋に収穫されるため、年明けすぐの1月では税金を納める準備が整わず、現実に合わせるために4月スタートとするのが理にかなっていたのです。
さらに、当時の世界経済で大きな影響力を持っていたイギリスも、4月を会計年度の始まりとしていたことから、日本も国際基準に合わせる形で4月を採用しました。
これには、国際社会との連携を深めたいという意図もあったと考えられています。
子供に「年度初め」を説明する時はどうすればいい?
ここでは、子供にも「年度初め」を分かりやすく説明するアイディアについてまとめています。
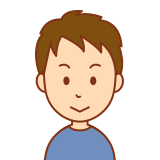
ねえ、なんで学校って4月から始まるの?お正月に年が変わるのにさ。
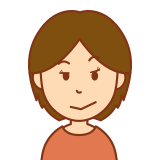
いい質問だね!実はね、日本では昔から会計年度が4月にスタートする仕組みだったんだ。これが始まったのは明治時代の1886年で、ちゃんと理由があるんだよ。
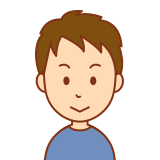
どんな理由なの?
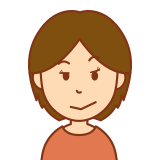
日本の税金は、昔はお米に大きく頼ってたんだ。農家が秋に稲を刈って、それを売ってから税金を納める流れだったから、年明けすぐに税金を集めるのは無理があったんだ。それで、収穫後に余裕を持たせて4月から新しい年が始まることにしたんだよ。それに、イギリスも4月から会計年度が始まってたから、世界の流れにも合わせたんだって。
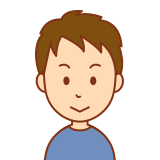
そっか〜。じゃあ、学校もそれに合わせたってこと?
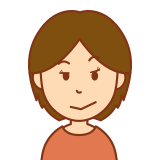
その通り!昔の学校は、好きなときに入学できる自由なスタイルだったんだけど、会計年度に合わせて4月スタートにしたんだよ。あとね、6月って梅雨でジメジメするでしょ?その時期に試験をするより、4月に新学期を始めた方が生徒たちにもよかったんだ。
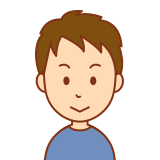
ふーん、日本ならではのやり方なんだね!
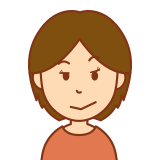
そうだね。海外だと9月に新学年が始まる国が多いけど、日本は桜が咲く季節に新しい生活がスタートするから、特別な感じがするよね。
子供から「年度初めが4月から始まるのはどうして?」と質問された場合は、主に「昔の学校との違い」などを説明してあげるといいでしょう。
まとめ
今回は、日本における「新年度」の始まり方などについてまとめました。
日本では、新年度や学校の学年の切り替えが4月に行われるのが一般的となっています。
これは、明治時代に制定された会計年度に起源があり、その後、全国の学校で4月始まりの制度が広まりました。
昭和時代にはこの流れがさらに定着し、戦後には新卒の一斉採用文化も生まれ、民間企業も自然と4月を年度のスタートとするようになりました。
一方、世界の多くの国では新学期は9月に始まるのが標準ですが、日本では新年度・新学期・入学式・入社式が4月に集中しています。
春に満開となる桜の季節と新しい門出が重なるため、これが日本独自の文化的イメージとしてしっかりと根付いているのです。


