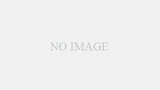いつでも手軽に食べることのできる食品の一つといえば、コンビニのおにぎりではないでしょうか?
バリエーションも豊富なので、コンビニに立ち寄った時は、ついつい手に取ってしまいます。
…とはいえ、「セールが行われた時にまとめ買いしたものの、食べ切ることができずに余らせてしまった!」という経験はございませんか?
コンビニおにぎりは基本的に日持ちが短く、賞味期限に関しても、たったの1日程度となっています。
すぐに食べる予定がないときは、冷凍して保存するという手段を活用するしかないでしょう。
本記事では、冷凍保存に向いている具材・避けたほうが良い具材、海苔の扱い、冷凍・解凍の方法、さらには冷凍後のアレンジ方法まで、実体験を元に紹介していきます。
コンビニおにぎりは冷凍保存できる?
セブン-イレブンやファミリーマート、ローソンなどのコンビニおにぎりは、実は家庭でも問題なく冷凍可能です。
冷凍食品として販売されているおにぎりがあることからも分かるように、ご飯の冷凍には大きな支障はありません。
正しい方法で解凍すれば、炊きたてのようなふっくらとした食感を楽しむことができます。
冷凍保存できる期間と消費の目安
コンビニのおにぎりを冷凍保存する際は、保存環境に気を配ることで、美味しさをキープできます。
冷凍保存が可能な期間と消費するまでの目安は、以下の通りです。
・美味しく食べられるのは2週間以内が理想
冷凍することで賞味期限は延ばせますが、長期間経過すると香りや味わいがやや損なわれることも…
特に家庭用の冷凍庫は扉の開閉が多く温度が安定しにくいため、品質の低下が早まる場合があります。
冷凍した日をメモしておくと、食べ頃を逃さず管理がしやすくなるでしょう。
冷凍できるコンビニおにぎりの上手な活用方法
コンビニで手に入るおにぎりは、その多くが冷凍保存に対応しています。
特に梅干しや焼き鮭、昆布といった伝統的な和風の具材は、冷凍しても味や食感が損なわれにくく、保存に向いていると言えるでしょう。
一方で、マヨネーズを使ったものや揚げ物、魚卵などの生もの系は、解凍後に風味や質感が変わりやすいため、冷凍にはあまり適していません。
コンビニおにぎりの冷凍を行う際は、パッケージのまま冷凍庫へ入れるだけでOKです。
風味を保ったまま楽しめる期間は約2週間で、最大で1ヶ月ほど保存が可能です。
食べるときは、電子レンジ(600W)でおよそ1分20秒ほど加熱すると、ふっくらとした状態に戻せます。
もし、解凍後に食感が気になるようであれば、焼きおにぎりにしたり、お茶漬けや雑炊風にアレンジすることで、美味しく食べ切ることが可能となるでしょう。
冷凍に向いている具材&避けたい具材の一覧
コンビニのおにぎりにはさまざまな種類がありますが、冷凍に向くもの・不向きなものがあるのをご存じですか?
選び方を間違えると、味や食感が大きく損なわれることもあるので注意が必要です。
冷凍するのに向いている具材リスト
以下のような具材の入ったコンビニおにぎりは、冷凍するのに適していると言えるでしょう。
・焼き鮭
・おかか
・昆布
・わかめ
・野沢菜
・高菜
・のりの佃煮
・納豆
・赤飯
・チャーハン、オムライス、チキンライスなど味付きご飯系
・とり五目、かやくご飯、混ぜご飯系
・塩むすび(具なし)
これらは、水分が少ない上に、保存性の高い素材が多いため冷凍するのに向いています。
特に梅干しや鮭のように塩分を含む具材は、冷凍しても味の変化が少なく安心です。もち麦入りのご飯も冷凍OKです。
冷凍するのに不向きな具材リスト
以下のような具材は冷凍後に味が落ちたり、食感が悪くなったりするため、避けたほうが無難です。
・ネギトロ、いくら、生たらこ、明太子
・唐揚げ、かつ、天むす、かき揚げ
・豚キムチ、牛しぐれ煮
・煮卵(味玉)
マヨネーズを含む具材は、冷凍・解凍によって分離しやすく、風味が落ちがちです。
ネギトロやいくらといった生もの(主に海鮮類や魚介類など)も、解凍後の品質劣化が避けられません。
また、揚げ物系は油が酸化しやすく、再加熱時に衣がふやけるためおすすめできません。
味付き卵は冷凍によって白身が硬くなりやすく、さらに電子レンジで爆発するリスクもあるので注意が必要です。
コンビニおにぎりを冷凍保存する際の基本ルール
コンビニで購入したおにぎりは、包装されたまま冷凍庫に入れるだけで簡単に保存できます。
直巻きタイプ(海苔がすでに巻かれているもの)も、パリッと海苔が別添えになっているタイプも基本的にはそのまま冷凍して問題ありません。
もし衛生面が気になる場合は、冷凍前にパッケージの外側を軽く拭いておくと安心です。
賞味期限が近いときの対処法
購入後すぐに食べきれない場合、特に賞味期限が迫っているおにぎりは素早く冷凍するのがポイントです。
アルミバットの上に並べて冷凍すれば、熱伝導の効果でスピーディーに冷凍できます。
バットがない場合は、アルミホイルを敷くだけでも代用可能なので、安心してください。
海苔も一緒に冷凍して大丈夫?
コンビニおにぎりの海苔についても、一緒に冷凍保存することが可能です。
乾燥している海苔は冷凍による劣化が少なく、基本的には風味を保ったまま解凍できます。
ただし、すでに巻かれている直巻きタイプでは、冷凍中に海苔がご飯の水分を吸って硬くなることがあります。
加熱することによって、食感は十分に戻るので、心配することはないでしょう。
おにぎりを美味しく解凍するためのコツ
冷凍したおにぎりを実食する際は、以下のような方法を用いて、解凍するのに一工夫をするといいでしょう。
・電子レンジで短時間加熱する
それぞれにメリット・デメリットがあるので、目的に合わせて使い分けましょう。
冷蔵庫でじっくりと解凍する場合
冷蔵庫に移して6時間ほどかけながら、ゆっくりと自然解凍する方法です。
気温が低い時期なら、室温でも2〜3時間くらいで食べ頃になります。
ただし、ご飯の水分が抜けやすく、やや硬く感じることがあるため、柔らかい食感を求める方にはやや不向きかもしれません。
電子レンジで軽く温めれば、もちもち感を復活させることが可能となるでしょう。
電子レンジで即時解凍する場合
もっとも手軽なのは電子レンジを使った加熱解凍です。
・600Wで1分30秒を目安に加熱
・温まりが足りない場合は10秒ずつ追加加熱
包装を外さずにそのまま温めることができ、海苔の風味も十分に楽しめます。
もし海苔が気になる方は、取り外して別で温めてもOKです。
レンジの出力に応じた加熱時間の目安は以下の通りとなっています。
・800W:約1分10秒
・1000W:約55秒
注意点として、明太子や生たらこなどの具材は加熱により食感が変化しやすいため、加熱時間には注意が必要です。
食べられないわけではありませんが、風味や舌触りに違いが出ることがあります。
直巻きタイプのおにぎりの加熱ポイント
ご飯に海苔が巻かれている直巻きタイプのおにぎりも、電子レンジでの加熱が可能です。(※目安は600Wで約1分20秒。)
海苔の食感は若干変わりますが、味そのものは損なわれず、美味しく頂けます。
冷凍おにぎりを活用する簡単アレンジレシピ集
冷凍状態で保存していたおにぎりは、解凍後にそのまま食べるだけでなく、ひと手間加えることで美味しさがグッと引き立ちます。
乾燥が気になる場合にも、以下のようなアレンジレシピが有効です。
焼きおにぎりにアレンジする
冷凍おにぎりの代表的な再活用レシピとして「焼きおにぎり」があります。
具材の種類を問わず、和風・洋風どちらでも楽しめる万能メニューです。
「焼きおにぎりアレンジレシピ」の作り方・手順は、以下の通りとなっています。
2.醤油やみりんベースのタレを塗る
3.両面に焼き目がつくまで中火で加熱
外はカリッと、中はふっくらという冷凍おにぎりとは思えない食感を満喫できます。。
そして、香ばしさとタレの風味で、冷凍感が気にならなくなるのも魅力です。
お茶漬け風にアレンジする
さっぱりした味わいを楽しみたいなら、解凍したおにぎりをお茶漬けにするのがおすすめです。
「お茶漬け風アレンジレシピ」の作り方・手順は、以下の通りとなっています。
2.市販のお茶漬けの素をふりかける
3.熱湯を注ぎ、箸で軽くほぐす
トッピングに白ごま、わさび、刻み海苔などを加えると、見た目も味も本格的になります。
おじや(雑炊)風にアレンジする
寒い日や体調が優れないときには、温かいおじやにするのも一案でしょう。
「おじや(雑炊)風アレンジレシピ」の作り方・手順は、以下の通りとなっています。
2.冷凍されたおにぎりをそのまま投入
3.お米がふっくらするまで弱火で煮込む
4.最後に溶き卵や刻みねぎを加えると、さらに美味しくなります
冷凍おにぎりとは思えないほど、優しい味わいが楽しめます。
これらのアレンジを活用すれば、冷凍おにぎりも立派な一品に早変わりするでしょう。
忙しい日や食材が少ないときでも、手軽に食卓を豊かにできるのが魅力です。
まとめ
コンビニおにぎりは、正しく冷凍すれば美味しさを長持ちさせることができます。
特に梅や鮭、昆布などの和風具材は冷凍に向いており、風味や食感の変化も少なく安心です。
ただし、マヨネーズ系や揚げ物、生ものなどは冷凍に不向きで、解凍後に味や品質が落ちやすいため注意が必要です。
冷凍する際は、パッケージごとそのまま保存可能で、冷凍庫での保存期間は最長で約1ヶ月です。(美味しく食べるには、2週間以内の消費が理想です。)
電子レンジでの加熱解凍や、冷蔵庫での自然解凍も可能ですが、乾燥が気になる場合は、焼きおにぎりやお茶漬け、おじやなどにアレンジすることで、最後まで美味しく楽しめます。
ちょっとした工夫で、余ったおにぎりも無駄にせず、美味しく活用できるので、ぜひ日常の食卓や保存食のひとつとして取り入れてみてください。