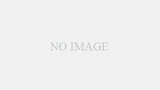「中秋の名月」と聞くと、まんまるなお月さまとお団子、そしてすすきを思い浮かべる人が多いでしょう。
ですが、「どうしてお団子をお供えするの?」と問われると、意外と答えに困ってしまう人も少なくありません。
どのような意味が込められているのかを知っておいた方が、ありがたい気持ちでお月見を行うことができるようになるでしょう。
そこで本記事では、中秋の名月にお団子を供えるようになった理由や、その風習のルーツなどについて分かりやすく紹介していきます。
「中秋の名月」とはどんな日?
「中秋の名月」とは、旧暦で8月15日にあたる日の月を指しています。
“中秋”とは文字通り“秋の真ん中”という意味で、今の暦ではおおよそ9月から10月頃にあたります。
旧暦では15日は満月に近い日であり、秋は空気が澄んで月がいちばん美しく見える季節です。
そのため、この日の月は「名月(めいげつ)」として特別に愛でられるようになりました。
日本で月見の風習が始まったのは平安時代とされており、貴族たちは月を眺めながら和歌を詠んだり、宴を開いたりしてその美しさを楽しんでいました。
その後、月の満ち欠けが稲や作物の実りと結びつけられるようになり、「月=豊穣の象徴」「神聖な存在」として大切にされていったのです。
お団子とすすきを供える理由
もともと中秋の名月は、秋の収穫を感謝する行事――いわば“収穫祭”でもありました。
江戸時代になると、収穫した作物(特に芋)を月にお供えして、自然の恵みに感謝する風習が広まります。
そのことから、この日は「芋名月(いもめいげつ)」とも呼ばれるようになったのです。
やがて、時代が経過していくとともに、実際の芋に代わって「丸いお団子」を供えるようになりました。
丸い形には「満ちる」「円満」といった縁起の良い意味が込められ、家族の健康や幸せを祈る象徴とされています。
また、月見のお供えに欠かせない“すすき”は、もともと稲穂の代わりとして用いられました。
秋の稲刈り前で稲を供えることが難しかったため、稲穂に似たすすきを代用したのです。
さらに、すすきには魔除けの力があるとされ、邪気を払うお守りのような意味合いもありました。
なぜ「中秋の名月」にはお団子を食べるの?
もともとお月見で供えられていたのは、里芋などの“芋類”だったと伝えられています。
やがて、主食であるお米の収穫に感謝を込めて、米粉を使ったお団子をお供えするようになったのです。
丸い形のお団子は、満月を模したものとされており、円満や調和の象徴でもあります。
ただし、地域によっては少し形が異なり、丸くないものや三色団子をお供えするところもあるようです。
また、秋は実りの季節でもありますから、お団子だけでなく、栗・柿・梨などの果物や新穀を一緒に供える地域もあります。
それぞれの土地で、収穫の喜びを分かち合う心が形を変えて受け継がれているのですね。
お供えをした後は、そのお団子を「ありがたくいただく」ことも大切な習わしです。
神社などで“お下がり”をいただくように、神様に供えたものを分けてもらうという意味があり、神聖な力を授かることで、感謝の心と豊かさを共有するという願いが込められています。
つまり、お団子を食べる行為そのものが、神様とのご縁を深め、自然の恵みへの感謝を表す儀式なのです。
お供えするお団子の数には決まりがあるの?
お月見団子と聞くと、ピラミッドのように積み上げられた姿を思い浮かべる人も多いでしょう。
実は、この「お供えするお月見団子の数」は偶然ではなく、幾つかの説があります。
・もう一つは、十五夜にちなんで「15個」とする説。
十五夜の並べ方には定番があり、下段に9個・中段に4個・最上段に2個を並べる形が一般的です。
ただし、家庭でお祝いする場合は、堅苦しく考えすぎず、家族の人数分を用意して楽しむのも素敵です。
風習の意味を理解したうえで、家族の形に合ったお月見スタイルにアレンジすることこそ、現代に合った“感謝のかたち”なのかもしれませんね。
まとめ
今回は、「中秋の名月」に込められた意味や、お団子をお供えする理由などについてまとめました。
中秋の名月にお団子をお供えするのは、「自然の恵みへの感謝」と「神様とのご縁」を大切にするという古くからの日本の心が形になった風習です。
元々は芋や穀物などを供えていたものが、やがて丸いお団子に変わっていき、満ちゆく月のように“円満”や“豊かさ”を象徴するようになりました。
また、お供えしたお団子を家族で分け合って食べることには、神様からの恵みをいただき、みんなで幸せを分かち合うという意味があります。
十五夜の夜は、空を見上げながら静かに月を眺め、感謝の気持ちとともに温かいお団子を味わってみてください。
きっと、古来から受け継がれてきた“祈り”の時間を感じられるようになるはずです。