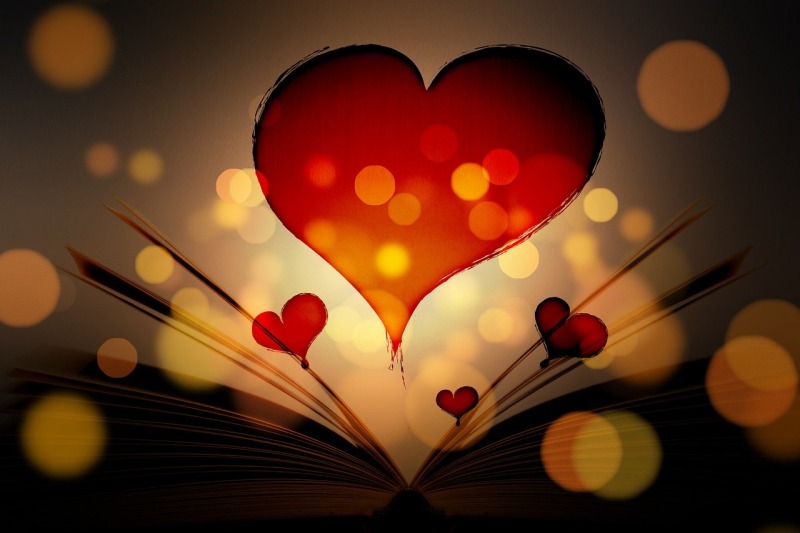夏休みにおける定番の宿題といえば、読書感想文ではないでしょうか?
子供たちの間では「本を読むのは好きだけど、感想を書くのはちょっと苦手」「そもそも読書自体があまり得意じゃない…」と声も少なくありません。
いざ書こうとしても「何から書けばいいの?」と迷ってしまい、まっさらな原稿用紙を前に手が止まってしまう生徒も多いでしょう。
特に高学年になると、学校の先生から「もっと詳しく書きなさい」「最後までしっかり埋めること」と言われることもあり、プレッシャーを感じることもあるかもしれません。
そのような時こそ、読書感想文の正しい書き方を知っておくことで、スムーズに進められるようになるでしょう。
本記事では、読書感想文における本の選び方から下準備、文章の組み立て方まで様々なポイントを紹介していきます。
読書感想文の題材となる本の選び方について
読書感想文に取りかかる前に、まずは「どの本を読むか」がとても大切なポイントです。
ここでは、本選びのコツと、読む前のちょっとした工夫をご紹介します。
興味のあるジャンルから本を選ぼう
まず大切なのは、「読んでみたい!」と思える内容かどうかです。
関心のないテーマでは、読み進めるのも一苦労ですよね。
難しすぎない内容の本を選ぼう
たとえ6年生でも、4年生や5年生向けの読みやすい本を選んでもまったく問題ありません。
※ただし、低学年向けすぎる内容は避けておいたほうがよいでしょう。
表紙やタイトルの印象を大事にしよう
「なんだか気になる…」というような直感も大切にしましょう。
表紙やタイトルを見てワクワクしたなら、それは良い出会いかもしれません。
ページ数が少なめの本もおすすめ
本を読むことや感想文に苦手意識があるなら、分量が少ない本からスタートするのが安心です。
そのような本の方が内容も把握しやすいので、感想文もまとめやすくなります。
主人公の成長を描いた作品は書きやすい
読書感想文の題材として、「成長していく主人公の物語」を選ぶといいでしょう。
読者の心にも響きやすく、自分自身と重ねて考えることができるため、感想文にもしやすいジャンルです。
読書感想文を書く際に必要となる物を準備する
さて、感想文の題材となる本が決まれば、読書前の準備を整えておきましょう。
ふせんを活用しよう
読みながら「印象に残った場面」や「物語の転機」と思える部分にふせんを貼っていきましょう。
思いついたらどんどん貼ってOK!遠慮せずにどんどん活用していくことをおすすめします。
メモを取っておくと便利
ふせんを貼った場面について、自分の感じたことや疑問点などをその場でメモしておくと、あとで感想文を書くときにとても助かります。
本を選ぶ段階から、読む準備までをしっかり整えることで、感想文がぐっと書きやすくなりますよ。
準備を整えて、自信をもって読書感想文を書き始めてみましょう!
読書感想文の流れをつかもう!構成のポイントを解説
読書感想文を書くときは、文章の「流れ」を意識すると、とても書きやすくなります。
ここでは、「はじめ」「中」「おわり」の三つのパートに分けて、構成のヒントをご紹介します。
はじめに – 書き出しの工夫
書き出しでは、本の紹介や読み始めた理由を書くとスムーズです。
例えば、題材に選んだ本を手に取ったきっかけとして…
…というように、本の内容と合わせて簡潔に紹介してみましょう。
または、物語の主役にスポットを当てて紹介するのもおすすめです。
…と主人公の印象を述べておくと、分かりやすさがアップするでしょう。
中盤 – 感じたことや考えたことを書く
ここで活用するのが、読書中に準備しておいた「ふせん」や「メモ」です。
読みながら心に引っかかった場面について、「これはどういう意味だろう?」「自分だったらどうするかな?」と考えたり、自分自身の体験と照らし合わせて感じたことを書いてみましょう。
そして、感想文でとても大切なのが「特に心に残った場面」です。
とシンプルな感想を書くだけでは不十分なので…
…となぜ印象に残ったのか、理由を具体的に伝えると、ぐっと読みごたえが増します。
最後に – 感想のまとめ
締めくくりでは、本を読み終えたあとの自分の気持ちを、素直に書きましょう。
読む前と読んだ後で感じたことの変化を書くと、感想文の結びとしてとても良い形になります。
このように、順を追って書いていけば、読書感想文も自然に仕上がりますよ。
読書感想文を書くときのポイントと注意すべきこと(例文つき)
ここでは、読書感想文を書く際に気をつけたい点や、読みやすくするためのコツを紹介します。
タイトルには自分の感じたことを反映しよう
読書感想文を書く際は、内容だけでなく、タイトルも工夫するようにしましょう。
タイトルは、読んだ本の名前そのままではなく、内容にふさわしい印象的な言葉を使うと伝わりやすくなります。
自分の気持ちは具体的に書く
本を読んで、自分がどのように感じたのかを、できるだけ具体的に表現しましょう。
気持ちの動きを言葉にすることで、より伝わりやすい文章になります。
あらすじの書きすぎに注意しよう
読書感想文でありがちなのが、物語の内容を細かく書きすぎてしまうことです。
物語の流れを説明するのは最小限にとどめ、自分の考えや感じたことをしっかり書くようにしましょう。
「アンを迎えに行ったおじいさんが帰ってくると、おばあさんは男の子を望んでいたと話します。それを聞いたアンは悲しくなって…」
これでは、ただの物語の説明になってしまっているので、感想文とは言えません。
大切なのは「自分がどう思ったか」であり、まさに読書感想文という名の通り、感想が主役なのです。
ただ単に物語をなぞるだけではなく、どのように自分の心が動いたかを書くことを意識してみてください。
まとめ
今回は、小学校高学年における読書感想文を書くコツなどについてまとめました。
読書感想文と聞くと、難しく考えてしまいがちですが、大切なのは「うまく書くこと」ではなく、「自分がどう感じたか」を素直に伝えることです。
興味のある本を選び、ふせんやメモで自分の気持ちを残しておくと、いざ書くときにスラスラ言葉が出てくるはず!
構成の流れを押さえて、自分の心が動いた場面や思ったことを、具体的に書いてみましょう。
あらすじを長々と書くよりも「読んでどう思ったか」「自分ならどうしたか」を中心に書くことで、あなたらしい感想文になります。
ちょっとしたコツをつかめば、感想文は決してこわくありません。
是非この夏は、自分だけの「心に残る一枚」を書きあげてくださいね。