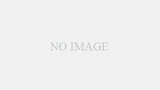「初めて迎えるお彼岸、どのように過ごせばよいのか分からない」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
特別な儀式をする必要はなく、通常のお彼岸と同じようにお参りを行えば十分なので、難しく考える必要はありません。
本記事では、初彼岸の基本的なマナーはどのようなものがあるのかなどについて説明していきます。
「初彼岸」とは?
「初彼岸(はつひがん)」とは、身近な人が亡くなってから最初に迎えるお彼岸のことを指します。
お彼岸は、春分・秋分を中心とした前後3日間(計7日間)に先祖供養を行う日本の仏教行事です。
年に2回ありますが、その中で「初めて迎えるお彼岸」が「初彼岸」と呼ばれています。
「初彼岸」の主な特徴について
故人が亡くなってから四十九日を過ぎ、初めてお彼岸の時期を迎えた場合に行われます。
したがって、四十九日より前に訪れるお彼岸は「初彼岸」には当たりません。(お彼岸は春分と秋分の年2回あり、日程は暦を見れば確認できます。)
遺族にとっては「節目」となる供養の機会であり、初めての年忌法要に近い重みを持つと考えられています。
墓参りや仏壇へのお供えを丁寧に行う家庭が多く、親族や知人から香典・お供物を贈る場合もあります。
「初彼岸」という風習の意味
初彼岸は「亡くなった人が仏様となって迎える初めてのお彼岸」とされ、故人を偲び、冥福を祈る大切な節目の行事です。
一般的に初彼岸を迎えることは「故人が無事にあの世へと渡った」と考えられており、墓参りをして供養するのが習わしです。
まとめると、「初彼岸」とは、大切な人を亡くしてから最初に迎えるお彼岸であり、特に丁寧に供養を行う時期と言えます。
初彼岸で頂いた香典のお返しマナー
初彼岸などのお彼岸は、家族そろってお墓参りをし、先祖や故人に感謝を伝える行事です。
「初彼岸だから特別な法要を必ず行わなければならない」という決まりはありませんが、普段より丁寧に供養を意識するご家庭が多いようです。
身近な親族が初彼岸を迎える際には、果物やお菓子といった供物に加え、香典として現金を包むこともあります。
そこで気になるのが「お金や品物をいただいた場合、お返しは必要なのか?」という点でしょう。
お彼岸の香典へのお返しは必要なのか?
基本的には「お彼岸のお供えに対してのお返しは不要」ということにされています。
ただし、地域の慣習や家族の方針によってはお礼を準備する場合もあり、その際はいただいた金額や品物の「3分の1〜半分」程度を目安にします。
たとえば、供物の金額相場は「3,000〜5,000円」程度とされるため、お返しは 1,000〜3,000円程度 が一般的です。
品物を選ぶ際は、タオル・洗剤などの生活必需品や、海苔・乾物といった日持ちする食品が無難です。
のし紙をかける場合は、黒白または黄白の結び切りを用い、表書きには「志」と記すのが一般的です。
渡す時期はいつが適切?
葬儀の香典返しは四十九日法要後に行いますが、お彼岸でのお返しは少し異なります。
お彼岸の期間は 春分・秋分の日を中心に前後3日を加えた7日間となっています。
このため、お礼の品は 彼岸明けを過ぎてから 相手に届けるのが望ましいとされています。
初彼岸での香典袋の選び方と書き方とは?
お彼岸には必ずしも香典を持参する必要はありませんが、お線香代わりに金封を準備して供える方も多く見られます。
特に遠方でお墓参りに行けない場合などに用意されることが一般的です。
香典袋の選び方
香典を包む際は、黒白または黄白の結び切りの水引が付いた不祝儀袋を使います。
結び切りには「繰り返さないように」という意味が込められており、慶事用の蝶結びとは区別されます。
水引の種類を誤るのは大変失礼にあたるため、購入時によく確認しておきましょう。
表書きは、故人が亡くなってから 四十九日より前であれば「御霊前」、四十九日を過ぎていれば 「御仏前」 と記します。
文字は水引の中央に書き、その下に差出人のフルネームを書き添えましょう。
書き方の注意点
表書きや氏名は必ず薄墨を使うのが弔事のマナーとなっているため、ボールペンは避けておき、薄墨用の筆ペンを準備しておきましょう。
ただし、中袋に金額や住所を記入する際には、ボールペンを使用しても差し支えありません。
金額は漢数字を用い、たとえば3,000円の場合は「金参千円」と書きます。(「四」は縁起が悪いとされるため避け、3,000円または5,000円を包むのが一般的です。)
金額が高すぎるとかえって相手に気を遣わせてしまうため、控えめにするのが望ましいでしょう。
お供え物と合わせる場合は、合計で5,000円程度を目安にすると無難でしょう。
また、新札は不幸をあらかじめ準備していたような印象を与えるため避けられます。
もしも、新札しか所持していない場合は、折り目を付けてから包むのが礼儀です。
服装のポイント
初彼岸では、特に法要を行わない場合は普段着でも差し支えありません。
ただし、華美な装いは避け、落ち着いた色合いの服を選びましょう。
もし法要に参列するのであれば、礼服を着用するのが基本です。
まとめ
初彼岸は、故人が四十九日を過ぎて初めて迎える大切な節目であり、特別な法要を行う必要はないものの、心を込めて供養することが大切です。
香典は必須ではありませんが、用意する場合は3,000〜5,000円程度が一般的で、不祝儀袋の表書きは「御霊前」と「御仏前」を使い分ける必要があります。
また、地域やご家庭の習慣によってお返しをする場合は、いただいた額の3分の1〜半額程度を目安に選びましょう。
服装については普段のお参りであれば落ち着いた装いを心がけ、法要に参列する場合は礼服を選ぶのが安心です。
持参する品は、日持ちのするお菓子や果物など、先方に気を遣わせないものが適しています。
大切なのは、形式にとらわれすぎず、故人を偲ぶ気持ちとご遺族への思いやりを持って行動することです。
マナーを押さえておけば安心して参列できますので、ぜひ参考にしてみてください。