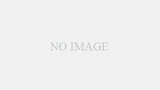皆さんは日常生活を送る中で「葉月(はづき)」という言葉を聞いたことはございませんか?
この言葉には、夏の名残を感じさせる情緒がありますが、この呼び名に込められた本来の意味は、私たちが抱く「真夏のイメージ」とは少し違っています。
本記事では、「葉月」という言葉の背景にある由来や意味を紐解きながら、同時に古くから伝わる別名や異称、この時期に行われる代表的な行事や習慣まで幅広く紹介していきます。
「葉月」とは何なのか?
「葉月」は、日本の旧暦における和風月名であり、八月のことを指しています。
古来より日本では、季節の移り変わりや自然の情景にちなんで、各月に独自の呼び名を与えてきました。
たとえば、一月を「睦月(むつき)」、二月を「如月(きさらぎ)」と呼ぶように、八月には「葉月(はづき)」という美しい名が付けられています。
この言葉は季節を象徴するだけでなく、響きの優雅さから人名としても人気があります。
特に女の子の名前に用いられることが多く、「和の趣がある名前」として親しまれています。
ただし、名付けの際には注意しておきたいポイントもあるので、覚えておいてください。
多くの人が「葉が茂る夏の盛り」というイメージでこの言葉を捉えがちですが、実は「葉月」は本来“葉が落ち始める時期”を意味しているのです。
「葉月」の持つ本来の意味と季節感
「葉月」という言葉を直感的に聞くと、緑豊かで生命力あふれる真夏を思い浮かべる人が多いかもしれません。
しかし、旧暦における「葉月」は、現在の暦とは約1か月から1か月半ほどずれがあります。
旧暦では、八月はすでに秋の入り口にあたり、立秋(8月7日頃)を過ぎたあたりの季節に該当します。
そのため、「葉月」という名には“葉が落ちる月”という意味が込められており、夏の終わりから秋の訪れを感じさせる情緒的な言葉なのです。
つまり、現代のカレンダーで8月を「葉月」と呼ぶとき、実際には旧暦でいう9〜10月頃の季節を指していることになります。
こうした背景を理解したうえで、「葉月」という名を使うと、より深い味わいが感じられるでしょう。
もちろん、名前として使う場合には「意味の解釈」にこだわりすぎる必要はありません。
たとえば「太陽の光を受けて輝く葉のように成長してほしい」という前向きな願いを込めるのも、とても素敵な発想です。
葉月とは、単に夏の名残を表す言葉ではなく、「季節の移ろい」を象徴する美しい日本語です。
夏の終わり、秋の始まりを告げるこの月には、古来より多くの行事や風習が息づいています。
その意味や背景を知ることで、「葉月」という言葉がいっそう深みのあるものとして心に残るでしょう。
「葉月」にまつわる異称とその意味
葉月には、古人が季節の情景や自然の変化を細やかに感じ取り、さまざまな別名を付けてきました。
そのどれもが、以下のように「秋の始まり」を美しく言い表しています。
・秋風月(あきかぜづき):涼やかな秋風を感じ始める頃を象徴しています。
・盛秋(せいしゅう):秋が深まり、実りが豊かになる様子を示す言葉。
・清秋(せいしゅう):澄み切った空気と清らかな秋の気配を指します。
・紅染月(こうそめづき):木々の葉が赤や橙に染まり始める季節を描いた名。
・壮月(そうげつ):夏の勢いをわずかに残した、生命力あふれる時期を意味します。
これらの異名からもわかるように、葉月という月は、夏から秋への移ろいを最も繊細に映す季節です。
日差しはまだ明るく、空気の中にほんの少しの涼しさが混じり始める――そんな微妙な季節の変化を、日本人は古来「葉月」という美しい言葉に込めてきたのです。
「葉月」の語源に隠された多彩な説
古くから人々の暮らしや自然の移ろいと深く結びついてきた「葉月(はづき)」という言葉には、いくつもの興味深い由来があります。
ここでは、その中で代表的な説を幾つか紹介していくことにします。
穂張り月(ほはりづき)説
最もよく知られるのは、稲の穂が膨らみ始める時期に由来するという説です。
旧暦でいう「葉月」は、まさに稲穂が実をつける頃にあたります。
そのため「穂が張る月」=「穂張り月」と呼ばれていたものが、時を経て音の変化から「はづき」へ転じたと考えられています。
初雁月(はつかりづき)説
もう一つの説では、この季節に北の国々から渡ってくる雁(かり)を最初に目にすることから、「初雁月」または「初来月(はつきづき)」と呼ばれていたとされます。
やがてこの呼び名も変化し、「はづき」という柔らかな響きに定着したと伝えられています。
葉落ち月(はおちづき)説
「葉月」という漢字が直接的に示しているのが、この説です。
旧暦の八月は実際には秋の入り口にあたり、木々が色づき始めて葉を落とす季節でした。
そのため、「葉が落ちる月」=「葉落ち月」と表現されたのです。
この説からもわかるように、葉月は“真夏”ではなく“秋の訪れ”を象徴する言葉だったことがうかがえます。
南風月(はえづき)説 ― ちょっと珍しい説
少し変わった説として、「南風月(はえづき)」という由来も存在します。
これは、南から吹く温かな風にちなみ名付けられたといわれています。
南風は夏を思わせる一方で、旧暦のこの時期は台風が発生しやすい季節でもありました。
そのため、「南風月」は自然の荒々しさと季節の変わり目を象徴する名でもあるのです。
こうした多様な由来をたどると、現代の“8月=真夏”という感覚と、旧暦の“葉月=初秋”という感覚のずれにも納得がいくでしょう。
葉月という言葉が、単なる季節名ではなく、自然の息づかいを写し取った言葉であることが見えてきます。
「葉月」に見られる風習や年中行事など
日本の旧暦で八月にあたる「葉月」は、実りの季節でありながら、自然の厳しさとも隣り合わせの時期でした。
そのため、古くから人々は豊作への祈りや、自然への感謝を込めたさまざまな行事を行ってきました。
ここでは、「葉月」における風習や年中行事の中で、代表的なものを紹介していきます。
八朔(はっさく)― 感謝と祈りの日
「八朔」とは、旧暦の八月一日を指す言葉で、「朔(さく)」は新月を意味します。
つまり、八朔は“八月の始まりの日”であり、農村では非常に大切な節目とされてきました。
この頃は稲穂が実り始める重要な時期であると同時に、台風などによる自然災害が多い時期でもあります。
そのため、人々は作物の無事な成長を祈り、日頃お世話になっている人々へ新穀や農作物を贈る風習が生まれました。
この行事は単なる収穫祭ではなく、地域のつながりや助け合いを確認する社会的な役割も持っていました。
恩義に感謝を伝える日であり、同時に「これからも共に支え合おう」という気持ちを形にした文化といえるでしょう。
なお、柑橘類の「はっさく」という果物の名前も、この日が語源とされています。
ただし実際の旬は冬から春にかけてであり、名前の由来と季節感が異なる点も興味深いところです。
八朔の風習は、自然と共に生きる日本人の知恵と、感謝の心を象徴する伝統の一つといえます。
「葉月」を彩る行事:お盆
「葉月」といえば、もう一つ忘れてはならないのが「お盆」という行事でしょう。
旧暦の八月(現在の七月中旬〜八月中旬頃)は、先祖の霊を迎え、感謝を捧げる大切な期間として古くから続いてきました。
お盆の由来と意味について
お盆は正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と呼ばれ、祖先の霊がこの世へ帰ってくるとされる仏教行事です。
家族は、霊を迎えるために灯りをともし、供物を捧げて手を合わせます。
・盆の明け・送り(16日):送り火を焚いて、霊を静かに見送る日。
この期間は、家族が集まり、故人を偲びながら心を通わせる大切な時間とされています。
地域ごとのお盆と行事
本来は旧暦の七月十三日〜十六日に行われていましたが、明治以降は新暦八月に行う地域が多くなりました。
たとえば徳島県の阿波踊りは、毎年八月十二日から十五日にかけて開催されるお盆の風物詩として有名です。
そのほか、京都の五山送り火や長崎の精霊流しなども、先祖の霊を送り出す行事として全国に知られています。
どの地域でも、お盆は「先人への感謝」「家族の絆」「命の循環」を感じる時期として今も大切に受け継がれています。
「葉月」に行われる八朔やお盆は、どちらも**「感謝と祈り」**を軸にした行事です。
人々は自然の恵みに手を合わせ、家族や地域とのつながりを確かめながら季節の節目を過ごしてきました。
こうした風習を知ることで、「葉月」という月が単なる暦の一ページではなく、日本人の心のリズムを映す季節であることがよくわかります。
まとめ
「葉月(はづき)」は、夏の終わりと秋の始まりが交わる、季節の転換点を象徴する美しい月名です。
その語源には「穂張り月」「葉落ち月」など、自然の移ろいを映したさまざまな説があり、古人の感性の豊かさを感じさせます。
また、八朔やお盆といった行事を通じて、人々は自然に感謝し、先祖とのつながりを確かめながら暮らしてきました。
つまり、「葉月」という言葉には、単なる暦以上に、“自然と人が寄り添う日本の心”が息づいていると言えるでしょう。