「おしるこ」と「ぜんざい」にどのような違いがあるのか気になったことはございませんか?
どちらも甘く煮た小豆に、餅や白玉を加えて頂く「和のスイーツ」の代表格だと言えるでしょう。
寒い季節にぴったりのスイーツで、食べると体の中からぽかぽかと温まってきますよね。
でも実は、この「おしるこ」と「ぜんざい」という名前や中身には、日本各地でちょっとした違いがあるんです。
例えば、こしあんかつぶあんかの違いだったり、スープのように汁があるかどうか、お餅なのか白玉団子なのかなど、細かいポイントで分かれています。
北海道、関東、関西、九州など、それぞれの地域で呼び方やスタイルに違いがあるため、一つの答えに決められないのも面白いところです。
一体「おしるこ」と「ぜんざい」にどのような特徴があるのかを見ていきましょう。
「おしるこ」と「ぜんざい」の語源とは?
まずは「おしるこ」と「ぜんざい」の語源や歴史について紹介します。
「おしるこ」の語源について
「おしるこ」という言葉は、「お汁粉」という漢字で書かれ、そのルーツを辿ると、江戸時代にまで遡ります。
当初は今のような甘いテイストの料理ではなく、塩味の料理だったとも言われています。
もともとは「餡汁子餅(あんしるこもち)」と呼ばれており、「餡入りの汁に餅を入れたもの」を意味していました。
やがて言葉が省略されて「汁子(しるこ)」となり、現在の「汁粉」という表記で広まりました。
「ぜんざい」の語源について
「ぜんざい」は、漢字で「善哉」と書きますが、その由来には複数の説があります。
ひとつは、仏教用語であるサンスクリット語の「善哉(ぜんざい)」から来ているという説で、「素晴らしい」「よいかな」といった意味が込められています。
この言葉を、一休宗純という僧侶がこの甘味を口にした際に感嘆して用いたことが由来だとする説です。
もうひとつは、出雲地方で行われる「神在祭(かみありさい)」に登場する「神在餅(じんざいもち)」が元になったという考え方です。
この呼び名が時とともに訛り、「ぜんざい」へと変化し、それが「善哉」という縁起の良い言葉と結びついたとされています。
各地域の「おしるこ」と「ぜんざい」の特徴について
次に「おしるこ」と「ぜんざい」の意味が、地域によって異なるのかを見ていきましょう。
関東地方における「おしるこ」と「ぜんざい」の違い
関東では、「おしるこ」と「ぜんざい」を区別する際のポイントは“汁気の量”です。
・ほとんど汁がないタイプ → 「ぜんざい」
さらに、使われるあんこの種類によっても名称が細かく分かれることがあります。
たとえば、粒あんを使ったものは「田舎しるこ」や「小倉しるこ」と呼ばれることがあり、反対にこしあんを使ったものは「御前しるこ」と表現されることも。
こうした呼び名のバリエーションを知ると、より一層その地域ならではの食文化が楽しめます。
関西地域における「おしるこ」と「ぜんざい」の違い
関西では、主に小豆の状態によって呼び名が変わります。
・豆の形が残るつぶあんを使ったもの →「ぜんざい」
また、関西特有の名称として、汁気のないあんこを使った甘味に「亀山」や「金時」といった呼び方があり、これらも地域ならではの呼称文化として根付いています。
北海道における「おしるこ」と「ぜんざい」の違い
北海道では、「おしるこ」と「ぜんざい」をはっきりと分ける習慣があまり見られません。
多くの地域では「おしるこ」の名称が主に使われ、「ぜんざい」という言葉を耳にする機会は少ないようです。
注目したいのが、北海道特有の「かぼちゃしるこ」という表現でしょう。
こちらは餅や白玉の代わりにかぼちゃを加えて楽しむスタイルで、かつては餅の代用品としてかぼちゃが使われていた背景があり、その名残として今でも親しまれています。
九州地方における「おしるこ」と「ぜんざい」の違い
九州では、小豆の仕上げ方によって「おしるこ」と「ぜんざい」の呼称が変わります。
こしあんを使ったものは「おしるこ」、つぶあんを使ったものは「ぜんざい」と呼ばれるのが一般的です。
こうした点を見ると、関西以西の地域では似たような分類がなされているようですね。
さらに一部のエリアでは、加える具材によっても名称が変わることがあります。
たとえば、餅が入っていると「おしるこ」、白玉団子が入っていると「ぜんざい」とするケースや、その逆のケースも見られ、地域ごとの多様性がうかがえます。
子供に「おしるこ」と「ぜんざい」の違いを説明する場合
子供に「おしるこ」と「ぜんざい」の違いを説明する場合のシミュレーションです。
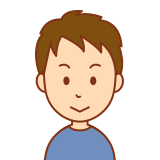
ねえねえ、“おしるこ”と“ぜんざい”って、どう違うの?
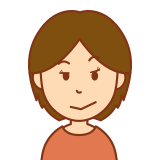
いいところに気がついたね!どちらも甘い小豆を使った日本のスイーツだけど、実は作り方や呼び方が地方によって少しずつ違うんだよ。
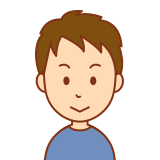
へー!それってどんな風に違うの?
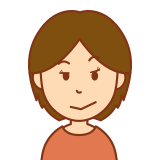
たとえば関東では、“おしるこ”は汁がたっぷりあるもの、“ぜんざい”はあんまり汁がないものって分けているんだ。
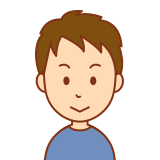
なるほど~!汁の量で名前が変わるんだね。他のところは?
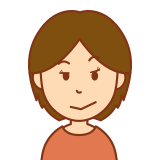
関西ではね、小豆のつぶし方で呼び名が変わるんだよ。なめらかな“こしあん”を使っていれば“おしるこ”、粒が残った“つぶあん”なら“ぜんざい”って言うんだ。
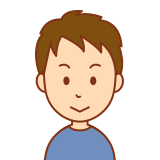
関西スタイルだと“おしるこ”なんだね!
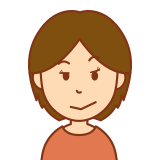
そうだね!どっちも体が温まるおいしい甘味だから、寒い日に一緒に食べようね。
地域によって、どのような違いがあるのかについて着目してください。
まとめ
今回は「おしるこ」と「ぜんざい」の違いや、地域ごとの特徴についてまとめました。
どちらも甘く煮た小豆を使った和風デザートで、加える具材や汁の量、小豆の形状などによって呼び名が変わります。
関東では汁の多さが基準になり、関西ではあんこのタイプによって区別されます。
また、それぞれの名前の由来にも地域の歴史や文化が反映されており、とても興味深いものです。
寒い季節には、家族でこうした甘味を囲みながら、地域のちがいについて話してみるのも楽しい時間になりそうですね。


