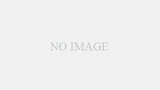七五三は、日本で古くから受け継がれてきた子どもの成長を祈願するための伝統行事として知られています。
この行事では、幼い子どもが無事に大きくなっていくことを願い、決まった年齢の時に神社へ参拝するのが特徴です。
一般的には3歳・5歳・7歳を節目として行われますが、性別(男の子or女の子)によって参拝する年齢が異なる場合があります。
本記事では、なぜこの3つの年齢が重要視されてきたのか、その背景と、性別ごとのお祝いの慣習についてわかりやすく説明していきます。
七五三の起こりと背景
七五三にまつわる風習は、今から遥かに昔の江戸時代に形づくられたとされています。
当時は幼い子どもの命が失われることも多く、生きて年齢を重ねられること自体が大きな喜びでした。
そのため、節目を迎えるたびに「無事に成長できますように」と神様に祈る文化が広まっていきました。
特に有名なのが、五代将軍・徳川綱吉が息子の健康を願って、旧暦11月15日に神社に参拝したと伝えられている話です。
この出来事が七五三の習慣が一般の人々にも広まるきっかけになったと言われています。
現在では、旧暦から新暦へ移行した後も11月15日が七五三の日として定着し、全国の神社で子どもたちの成長を祈る姿が見られます。
七五三で祝う「3歳・5歳・7歳」の意味とは?
日本では、子どもが3歳・5歳・7歳になる節目に神社へ参拝し、これまでの成長に感謝し、これからの健やかな日々を願う風習があります。
この習わしのルーツは平安時代の宮中行事にまで遡り、身分の高い家庭で行われていた子どもの成長儀礼が少しずつ庶民にも広まっていきました。
現在は11月15日が七五三の日として定着していますが、この日は昔から「子どもの厄を祓い、運を強める」とされる特別な日でした。
それぞれの年齢に対応した儀礼には、当時の子どもの発育段階や社会での位置付けが反映されています。
3歳:髪置(かみおき)
この頃になると、赤ちゃんから幼児への変化がはっきりしてきます。
昔は剃っていた髪をこの日から伸ばし始めることで、「ここから本格的に成長していきます」という区切りを示しました。
子どもが初めて“自分らしさ”を持ち始める時期を祝う儀式として大切にされていました。
5歳:袴着(はかまぎ)
5歳の男児は、初めて袴を身につけることで“社会の一員”として扱われるようになります。
武家社会で特に重要視され、この服装に変わることで精神的な独立や自覚が芽生えると考えられていました。
7歳:帯解(おびとき)
7歳の女児は子ども用の着付けから離れ、大人と同じように帯を結ぶようになります。
これは、少女から一歩大人の女性へ近づく節目を象徴する儀式であり、品位をもって成長していくことを願う意味が込められています。
これらの儀式は、単なる衣服の変化ではなく、「子どもが社会的に認められていく」通過点として大切にされてきたのです。
男児と女児で七五三の対象年齢が異なる理由
古くから行われてきた七五三には、男の子と女の子でお祝いする年齢が異なっています。
男の子は3歳と5歳、女の子は3歳と7歳でお参りすることが一般的です。
では、なぜ違いが生まれたのでしょうか?…その答えは、取り入れられていた儀礼内容にあります。
3歳の「髪置」だけは男女共通の節目として祝われましたが、その後の儀式は性別で分かれていました。
5歳に行う「袴着」は男の子が初めて袴を身につける大切な機会であり、武家社会における“男性としての準備”の側面が強い儀式でした。
一方、女の子の「帯解」は7歳の頃に行われ、帯を締めることで“大人の女性の仲間入りの第一歩”という意味を持ちます。
このように、それぞれの儀式が行われる年齢が異なるため、現在の七五三も男女で祝うタイミングが違う形で残っているのです。
また、昔は「数え年」で行うのが一般的でしたが、現代では「満年齢」でお祝いする家庭も多く、どちらを選んでも問題ありません。
地域や家族のしきたりによって異なるので、相談してその家庭に合った形でお祝いすると良いでしょう。
兄弟姉妹の七五三をまとめてお祝いするには?
兄弟姉妹の年齢が近いと、七五三のたびに毎年準備をしなければならず、家族にとって負担になることがあります。
特に親族を呼んだり、写真撮影をしたりする場合、年ごとに同じ規模の行事を繰り返すのは大変です。(遠方に住む祖父母がいる家庭ではなおさらでしょう。)
そこで便利なのが、「満年齢」と「数え年」をうまく組み合わせてスケジュールを調整する方法です。
たとえば、上の子が満5歳、下の子が満2歳の年であれば、上の子は満年齢の5歳、その一方で下の子は数え年として3歳とみなし、同じ年に兄弟そろって七五三を祝うことができます。
このように、それぞれの年齢の数え方を柔軟に利用することで、家族の負担を減らしつつ、兄弟姉妹が一緒に記念日を迎えられるメリットがあります。
なお、「満年齢」と「数え年」には、以下のような違いがあります。
・数え年:生まれた時点で1歳とし、毎年1月1日に一つ年を重ねる昔ながらの方法
この計算方法の違いにより、数え年では多くの場合、実際の年齢より1〜2歳上になることがあります。
早生まれの子どもはいつ七五三を迎える?
1〜3月生まれの子、いわゆる「早生まれ」の七五三のタイミングは、多くの家庭が迷いやすいポイントです。
11月15日が七五三の日とされているため、誕生日が遅い子どもは、満年齢で考えるとお祝いが翌年にずれ込むことがあります。
昔は七五三を数え年で行うのが主流でしたが、現代では満年齢でお祝いする家庭も一般的になりつつあります。
そのため、「どちらが正しい」という決まりはなく、家庭の考え方や子どもの成長に合わせて選んで差し支えありません。
例えば、11月20日生まれの子どもがいる場合、数え年で3歳とみなすとその年に七五三を行えます。
一方で、体格や発育の状況を考えて「もう少し成長してから」と判断すれば、翌年に満3歳としてお祝いすることもできます。
七五三はあくまで「子どもの幸せと健やかな成長を祈るための行事」です。
華やかな装いや写真などに目が向きがちですが、最も大切なのは、家族が心を込めて子どもを祝うこと。
無理のないタイミングで、その子らしい思い出になる七五三を迎えてあげてください。
まとめ
七五三は、子どもの健やかな成長を願う日本ならではの大切な節目の行事です。
3歳・5歳・7歳という特別な年齢にお祝いを行うのは、平安時代から受け継がれてきた成長儀礼が元になっており、それぞれの年齢に応じた意味が込められています。
男の子・女の子でお参りの年齢が異なるのは、行われてきた儀式が性別によって違っていたためであり、現代では満年齢・数え年のどちらを選んでも問題ありません。
また、兄弟姉妹がいる家庭や早生まれのお子さんの場合も、どのタイミングで祝うかは柔軟に調整できます。
一番大切なのは、形式にとらわれ過ぎず、家族が笑顔で子どもの成長を喜べること。
お子さんのペースに合わせて、思い出に残る温かい七五三を迎えてください。