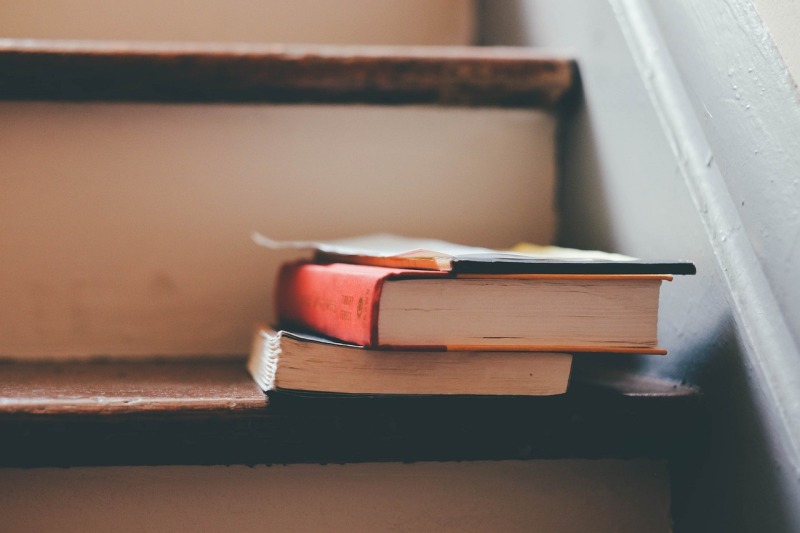学生の皆さんは、夏休みの宿題として読書感想文の提出を求められることもあるのではないでしょうか?
実際に感想文を書く時は「どのくらいの文字数が必要なのだろう?」と迷うこともあるのではないかと思われます。
原稿用紙を埋めていく作業は骨が折れる一方で、あまりにも短すぎる感想文は先生から叱責されるケースもあるので注意しなければなりません。。
読書感想文は「どれくらい書けばいいのか」という目安を知っておいた方が安心できるでしょう。
そこで本記事では、学生(小学生、中学生、高校生まで)を対象に、読書感想文にふさわしい文字数の基準や規定に届かない時の対処法などを解説していきます。
読書感想文における文字数の目安について
多くの場合は学校から「原稿用紙○枚程度」と指定されますが、そうした案内がないケースもあります。
そのような場合は「青少年読書感想文全国コンクール」の基準を参考にすると分かりやすいです。
コンクールで示されている文字数は以下の通りとなっています。
・小学校中学年(3・4年生):1,200字以内(約3枚/60行程度)
・小学校高学年(5・6年生):1,200字以内(約3枚/60行程度)
・中学生:2,000字以内(約5枚/100行程度)
・高校生:2,000字以内(約5枚/100行程度)
学年によって文字数の目安は変わってくるため、気を付けましょう。
文字数を数える際の注意点
コンクールに応募する際は、文字数の数え方にもルールがあります。
・句読点は1文字として計算する
・改行に伴う空白も字数に数える
たとえば小学校低学年の基準は800字ですが、この数にタイトルや氏名は含まれません。本文のみで数え、最終ページは上2行を使用すると計算しやすくなります。
評価が重視されない場合
成績や審査をあまり気にしなくてよい場合は、指定された字数の**およそ7割強(約75%)**を目標にすると安心です。
各学年ごとの読書感想文における文章量の目安は以下の通りとなっています。
・小学校中学年(基準1,200字):900字以上(約45行)
・中学生(基準2,000字):1,500字以上(約75行)
・高校生(基準2,000字):1,500字以上(約75行)
あくまで参考値なので、不安があれば担任の先生に確認しておきましょう。
良い評価を狙う場合
学校での評価を意識するなら、75%程度では少し物足りないと判断されることがあります。
もちろん文字数が多ければ自動的に高評価というわけではありませんが、一般的には字数を多めに書いた方が好印象になりやすいです。
・小学校中学年(1,200字想定):1,080字以上(約54行)
・中学生(2,000字想定):1,800字以上(約90行)
・高校生(2,000字想定):1,800字以上(約90行)
高評価を目指すなら、指定された文字数の9割以上を目安にしましょう。
コンクールで入賞を目指す場合
もしも、読書感想文コンクールで賞を狙う場合は、さらに指定文字数の95%前後を目指すとよいでしょう。
実際に受賞している作品は、文字数がぎっしりと書き込まれているものが多い傾向にあります。た
だし、字数だけで決まるわけではなく、あくまで内容の充実度との両立が大切です。
読書感想文のコンクールに応募する際の文章量の目安は以下の通りです。
・小学校中学年(1,200字想定):1,140字前後(約57行)
・中学生(2,000字想定):1,900字前後(約95行)
・高校生(2,000字想定):1,900字前後(約95行)
実際にどんな文章が評価されやすいのかを知るには、過去の受賞作品を読むことが一番の参考になります。
読書感想文で文字数が足りないときの工夫
「感想文を書いてみたけど、原稿用紙の空白が目立ってしまった…」という経験はございませんか?
ここでは、感想文の文字数を自然に増やすためのアイディアを紹介していきます。
あらすじを厚めに書く
どうしても分量を増やしたいときは、物語の流れを丁寧にまとめてみましょう。(特に登場人物の会話を引用すると、文章が膨らみやすくなります。)
ただし、内容の大半をあらすじで埋めてしまうと「感想文」というより「要約」になってしまうので、加減には注意が必要です。
印象的な場面を掘り下げる
あと数百字足りないときは、自分の心に残った場面を取り上げて、より詳しく考察してみるのがおすすめです。
具体的な書き方の例文サンプル事例は、以下の通りとなっています。
さらに充実させるなら次のような要素を加えると良いでしょう。
・そこから学んだこと
・自分が同じ立場にいたらどうするか
これらを活用した例文サンプルは、以下の通りです。
このような工夫を入れると、文章量だけでなく内容の深さも増していきます。
表現をふくらませる
短い感想を長めの言葉に置き換えるという手法も有効となるでしょう。
「感動しました」の代わりに…
・強い衝撃を受け、胸がいっぱいになりました。
・その勇気に心から感動しました。
「驚きました」の代わりに…
・予想もしなかった展開に目を見張りました。
・本当にそんなことが可能なのかと愕然としました。
「面白かったです」の代わりに…
・○○の場面は特に引き込まれるような面白さがありました。
・読み進める手が止まらないほど楽しめました。
このように言い換えると、文字数が増えるだけでなく表現も豊かになります。
ちょっとした調整で字数を増やす
「あと数文字だけ足りない」というときは、小さな工夫で解決できます。
・長い文を二つに分ける
・読点「、」を加える
実際にこれらを活用すると、以下のような文章になるでしょう。
こうすれば自然に文字数を増やせるうえ、文章も読みやすくなります。
読書感想文におけるその他のテクニック
読書感想文におけるその他のテクニックについても紹介していきます。
文字数を削るコツ
「文字数を減らす必要があるなんて滅多にない」と思うかもしれませんが、指定の上限を超えてしまうことは意外とよくあります。
そのような時に役立つ文字数を調整する方法についてまとめました。
・余分な読点「、」を省く
・細かく分けた段落をひとつにまとめる
・二つの文を一文に統合する
・回りくどい言い回しを、よりシンプルな言葉に置き換える
特に「です・ます」を「だ・である」に変えるだけでも文字数を大きく削減できます。
さらに、どうしても収まりきらない場合は、エピソードの一部を思い切って省略するのも手です。
読書感想文を書くときの基本姿勢
感想文を仕上げようとすると「完璧に書かなければ」と力んでしまいがちですが、まずは三割程度の完成度でいいから書き始めることが重要です。
・書き出したメモを整理し、文章へと発展させていく
取り組むときに考えるポイントは次のようなものです。
・自分がその場にいたらどう感じるか
・登場人物の性格や、自分との共通点
・本を通じて得られた学びやメッセージ
こうした要素をもとに、以下の流れで文章を構成すると書きやすくなります。
2.選んだ理由
3.あらすじの要約
4.本文(心に残った場面や感想の詳細)
5.まとめ
これで「読書感想文を書くのは難しい」というイメージもなくなるでしょう。
デジタル機器を利用した下書きの利点
スマホやパソコンを使って下書きをすると、手書きよりもはるかに効率的です。
・文字数の増減を調整しやすい
・手書きのように書き直しで苦労することがない
特にパソコンには文字数カウント機能が備わっていることが多く、上限や目標字数の確認が簡単にできます。
もし機能がなければ、オンラインの「文字数チェックサービス」を利用すると便利です。

文章をコピー&ペーストするだけで、瞬時に文字数を把握できるようになります。
まとめ
読書感想文は「何文字書けばいいのか」「足りなかったらどうすればいいのか」と不安になりがちですが、基本的な目安と工夫を押さえておけば安心です。
・目的に応じて(提出用・評価重視・コンクール用)必要な分量を調整する
・文字数が不足するときは「あらすじを少し詳しく」「心に残った場面を深掘り」「表現を言い換える」などで補う
・逆に多すぎるときは「常体への変更」「言い回しの簡略化」などで削る
一番大切なのは、無理に字数を稼ぐのではなく、自分の感想や考えを素直に表現することであり、数字はあくまで目安にすぎません。
読んだ本から感じ取ったことを、自分の言葉でしっかり伝えられれば、それが一番の読書感想文になります。