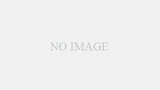学生時代の友人やクラスメイトたちと最近会ったのはいつ頃でしょうか?
小・中・高・大学と進むにつれて、昔の仲間と顔を合わせる機会はどんどん減っていきます。
そんな中で、久しぶりの再会の場として設けられるのが「同窓会」です。
懐かしい話に花が咲いたり、遠くに引っ越した人が久々に顔を出したりと、楽しみにしている人も多いのではないでしょうか。
ただし、その裏で頭を抱えている人もいます。そう、幹事を任される人です。
日程調整に連絡のやりとり、会場の手配や出欠確認……正直、負担が大きい役目なので「できれば遠慮したい」と思っている方も少なくないでしょう。
そこで今回は、「幹事なんて無理!」と思ったときに使える、角の立たない上手な断り方をご紹介します。
なぜ同窓会の幹事は敬遠されるのは何故なのか?
同窓会の幹事を任されることに、気が進まないという人は多いものです。
その最大の理由は、やはり「手間がかかりすぎる」ことに尽きるでしょう。
例えば、同じ地元に通っていた学校の仲間で集まる場合であれば、連絡手段も確保しやすく、計画も比較的スムーズに進む可能性があります。
近年はスマートフォンやSNSなどの普及によって、連絡網の整備も昔に比べて格段に楽になりました。
特に成人式などで地元に戻るタイミングと重なるような同窓会であれば、スケジュール調整もしやすく、参加者の確保もしやすいのが実情です。
一方で、進学や就職をきっかけに地元を離れてしまった場合には、話が大きく変わってきます。
離れた土地に住んでいる同級生たちを再び一カ所に集めるのは、至難の業です。
大学時代の仲間とキャンパス周辺で再会を企画する場合なども、事情は同様でしょう。
結局のところ、参加者の集まりにくさが増せば増すほど、幹事の負担も重くなり、「やりたくない」という気持ちが強くなるのです。
何故いつも同じ人が幹事なの?幹事を任される側の本音とは?
同窓会の幹事は、労力が多いため、誰にとっても気が重い役回りとなるでしょう。
そのため、「次は誰がやる?」という話になると、空気が重くなるのも無理はありません。
特に地元での開催が多い場合には、地元に残っている卒業生が幹事役を引き受けるケースが目立ちます。
その結果、毎度のように同じ顔ぶれが幹事を担当しているというパターンも少なくないようです。
こうした幹事たちが頭を悩ませるポイントには、次のようなものがあります。
・出欠確認の返事が遅く、人数の確定がなかなかできない
・参加の可否が曖昧な人がいて、対応に困る
・通知は郵送、返答はSNSやメールなど、手段がバラバラで整理が難しい
中でも連絡先が不明なケースの場合は、集まるのが容易ではなくなるでしょう。
進学や転職で住所が変わっている人も多く、名簿が存在しないことも珍しくありません。
さらに、いつも同じ人が幹事をしていることに周囲が慣れてしまい、連絡の返信を後回しにしたり、期日を守らなかったりと、だんだんルーズになっていく傾向も…
本来であれば、幹事にかかる負担を考えれば、周囲の協力がもっとあってもよいはずです。
「幹事だから大変なのは当たり前」と無関心になるのではなく、一人ひとりが少しでも配慮するだけで、ぐっと運営は楽になるのではないでしょうか。
同窓会の幹事を依頼された時に断ることは可能なのか?
さて、「いざ幹事をお願いされたとき、どうやって上手に断るか」…これは多くの人にとって悩ましい問題です。
前述のとおり、同窓会が地元で行われる場合、地元に住み続けている人に幹事の白羽の矢が立つことがよくあります。
というのも、準備段階では現地の店舗を探したり、会場を視察したりと、地元にいないと難しい作業が多く含まれるためです。
そのため、もし地元にいるけれど幹事は引き受けたくない…という場合は、「日程調整が難しい」「準備に関わる時間が確保できない」といった事情を伝えるのが効果的でしょう。
例えば、出張が頻繁で予定が読めない、あるいは妊娠中・育児中で長時間の外出が難しいなど、具体的な事情を添えて伝えれば、納得してもらえる可能性は高いです。
ただし、ひとつだけ気をつけたいのは、同窓会当日に参加するつもりがある場合です。
「動けない」という理由で断った手前、後から参加するのは矛盾に見えてしまうこともあります。
無理のない範囲で、状況に合った言い回しを工夫すると良いでしょう。
まとめ
今回は、同窓会の幹事を依頼されても上手に断る方法などについてまとめました。
同窓会の幹事は、地味ながらも多くの手間がかかる重要な役割だと言っても過言ではないでしょう。
頼まれると断りにくいものですが、自分に余裕がない時に無理して引き受ける必要はありません。
最大のポイントは、「同窓会の幹事をできない理由」をきちんと伝えておくことです。
曖昧な態度で引き延ばすより、早めに誠意をもって断った方が、相手も次の対応がしやすくなります。
幹事の仕事は一人で抱えるものではなく、本来は参加者全員が協力し合って作り上げるものですから、断ることに罪悪感を持たず、今の自分にできる形で関わっていく姿勢が大切なのです。